要支援1・2のサービスと料金
要支援1の1ヶ月の限度額は 5032単位、要支援2では10531単位です。基本的には、1単位=10円ですが、都市部では若干の割増料金となります。
要支援1・2向けのサービスを予防給付といいます。
予防給付のサービスは、利用者がサービスを利用することで、体の状態を維持、改善して、要介護にならないように予防すること(介護予防)を目標にしています。つまり、自力で生活することを支援するのが目的ですから、サービスで自活する力を落とすようなことがあってはいけません。
地域包括支援センターが中心となって、要支援1・2の人に介護予防のためのケアプランを作成します。
居宅サービス
居宅サービスは、自宅で生活をしながら利用する介護サービスです。有料老人ホームなどは自宅と同様とみなされ、入居者が居宅サービスを受けることができます。また、自宅での生活を支援するため、福祉用具の貸し出しや住宅改修の費用の補助も利用できます。
1)介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などで施設での浴室の利用が困難な場合などに限って、訪問による入浴介護を行います。
看護職員 1 人と介護職員 1 人で行った場合
| 1回あたり | 852単位 |
2)介護予防訪問リハビリテーション
通院が困難で日常生活の活動を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、作業療法士などの専門家が自宅を訪問してリハビリテーションを行います。
1 回の利用料は 20分未満で、 307単位です。要介護1-5 の人と料金は同じです。
| 1 回あたり(20分未満) | 307単位 |
3)介護予防訪問看護
通院が困難な人に、医師の指示に基づいて、看護師が自宅を訪問して看護サービスを提供します。一部の加算金を除いて、要介護1-5の人と料金は同じです。
| 20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1 時間30分未満 | |
| 訪問看護ステーション | 302単位 | 450単位 | 792単位 | 1087単位 |
| 病院・診療所 | 255単位 | 381単位 | 552単位 | 812単位 |
4)居宅療養管理指導
通院が困難な人に、医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の指導や助言を行います。居宅療養管理指導は、医師の指示に基づくもので、要介護度によって決められている支給限度額には含まれません。
医師による指導の場合(1回あたり、月2回まで)
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 514単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486単位 |
| それ以外の場合 | 445単位 |
5)介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで施設に通い、食事、入浴などの日常生活の支援、生活機能の維持や改善のためのリハビリテーションを行います。通所リハビリテーションができるのは、病院、診療所、介護老人保健施設などの医療機関のみです。食費は、全額、利用者の負担になります。
料金は1ヶ月あたり、要支援1が2053単位、要支援2が3999単位の2種類の定額制です。
1ヶ月あたりの料金
| 要支援1 | 2053単位/月 |
| 要支援2 | 3999単位/月 |
6)介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
ショートステイといわれるサービスで、福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)などは、別途負担する必要があります。
1日あたりの料金、従来型個室の例
| 要支援1 | 474単位 |
| 要支援2 | 589単位 |
7)介護予防短期入所療養介護
医学的な管理を必要とする人が、介護老人保健施設(老人保健施設)や介護療養型病院などの医療機関に短期間入所し、介護、看護の医療サービスを受けることができます。
料金は、施設、部屋、要介護度、 1 人あたりの職員の数などによって異なります。日常生活費(食費・滞在費・理美容代など)などは、別途負担する必要があります。
老人保健施設、1日にあたりの料金、従来型個室の例
| 要支援1 | 577単位 |
| 要支援2 | 721単位 |
8)介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅は、介護保険では利用者の自宅と考えられています。こうした施設に入居している人に、介護予防のための日常生活の支援や介護を提供します。
入居者は、入居施設が提供するサービスか、外部の事業所による介護サービスのどちらかを選んで利用することができます。入居費用・日常生活費(おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
1日あたりの料金
| 要支援1 | 182単位 |
| 要支援2 | 311単位 |
9)福祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修費支給
生活の自立支援に効果のある福祉用具(工事のいらない手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえなど)の貸し出しを行います。ただし、車いす、特殊ベッド、床ずれ防止用具など対象外となるものがあります。また、入浴や排泄などに必要な福祉用具を購入する費用が補助されます。
たとえば、腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽などが対象になります。ほかにも、手すりや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費用が補助されます。
地域密着型サービス
認知症や一人暮らしの高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように支援するサービスを、地域密着型サービスといいます。
介護予防を目的とした地域密着型サービスには、次のようなものがあります。
1)介護予防小規模多機能型居宅介護
通所介護、訪問介護、短期入所を1つの事業所が提供するもので、通いを主体に、訪問や泊まりを組み合わせるサービスです。
1ヶ月あたり、要支援1が3438単位、要支援2が6948単位の2種類の定額制です。日常生活費(食費・宿泊費・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
1ヶ月あたりの料金
| 要支援1 | 3438単位/月 |
| 要支援2 | 6948単位/月 |
2)介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人がデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事、機能訓練や日常生活訓練を行います。下表は、単独で運営されている事業所を、7時間以上8時間未満、利用した場合の1回あたりの料金です。送迎に係る費用も含まれています。食費やおむつ代などの日常生活費は別途負担する必要があります。
1回あたりの料金
| 要支援1 | 859単位 |
| 要支援2 | 959単位 |
3)介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の人が5-9人で共同生活をしながら、入浴や食事、機能訓練や日常生活訓練を行います。
対象は要支援2のみで、要支援1は対象外です。料金は1日あたり760単位です。日常生活費(食材料費・理美容代・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
1日あたりの料金
| 要支援1 | 対象外 |
| 要支援2 | 760単位/日 |
料金は、施設や事業所の規模や、サービスの内容などによって、違いがありますので、 ひとつの目安と考えてください。











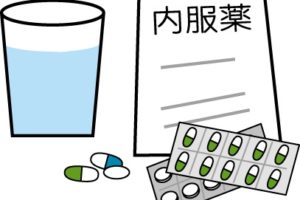


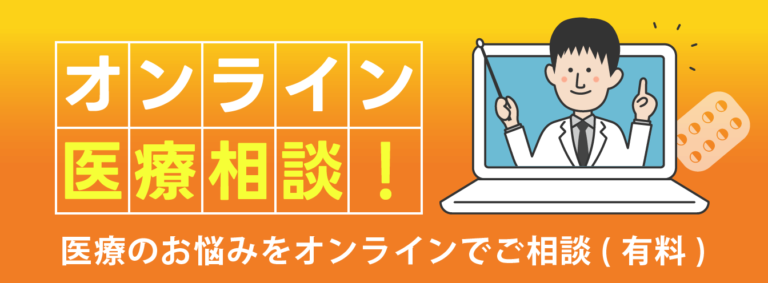

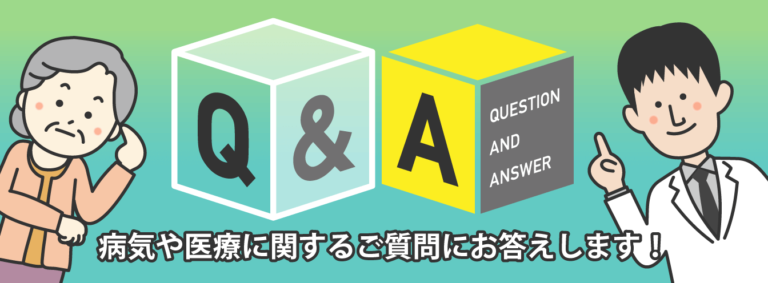
コメントを残す